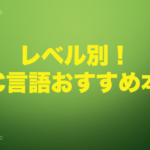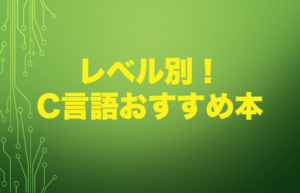組み込み入門第9段では入出力装置について解説していきます。
前回解説した入出力IFの先につくような装置として今回は出力装置と補助記憶装置について見ていきます。
目次
出力装置
代表的な出力装置を紹介していきます。
LED表示装置

LED表示装置は発光ダイオード=LEDを並べた表示装置です。LEDは電流を流すと単色で発光します。発光する色はLEDの素子ごとに固定です。電流変化により発光量が変わりますが、追従速度が早いため制御性が良いです。
また、赤、緑、青を用いてそれぞれの発光量を制御することでフルカラーの提示が可能です。
明るさ制御にはPWM(Pulse Width Modulation)という技術を使うこともあります。PWMについては、今後ハードウェアの記事を書く際に詳細に解説する予定です。
CRT(ブラウン管)

CRT(Cathode Ray Tube)はいわゆるブラウン管のことです。最近の若い方ではピンとこない方も出始めたかもしれませんね。蛍光体の塗布された面に順次電子銃で電子を当てて発行させる方式を取ります。蛍光体は光=電子を受けると別の色の光を発する性質を持つ物体です。3色の蛍光体を用意することでフルカラーを実現します。
応答性は良いですが皆さんご存知のように大きく重たいです。
液晶表示装置

LCDはいわゆる液晶ディスプレイのことです。身の回りの様々なディスプレイに使われていますね。液晶は電圧により、結晶の配列が変化する物質です。すると光の透過率や偏光が変わることで見え方が変わります。背面に光源を配置することで明るく表示することが可能です。
有機ELディスプレイ

有機ELディスプレイは電圧をかけると発光する物体の両側から電圧を印加する方式の表示機です。
発行体が非常に薄いため形状を自由に設計できます。さらに自ら発光するため視野角の問題がありません。このような性質から折りたたみスマホなどにも使われています。
LCDよりも動作寿命が短いため発光輝度や時間に配慮して無駄遣いしないような制御が必要です。
補助記憶装置
補助記憶装置の種類について俯瞰的に分類してみます。

補助記憶装置は、記憶の方法が磁気・半導体(電気)・光(物理形状)によりまず分類できます。さらに、コンピュータに常時接続しておくような固定式か、必要な場面で接続する交換式かでも分類します。
さらに特徴として連続的な読み書きをするシーケンシャルアクセスか不連続な読み書きをするランダムアクセスかがあります。磁気テープのようにテープに順番にデータを書き込むようなものは連続アクセスは早いですが、読み先のアドレスが進んだり戻ったりするようなランダムアクセスでは著しく性能が遅くなります。ディスク型のデバイスでも同様なことが言えますが、HDDのように半径方向に移動するアームが付いているものは幾分か早くなります。
また、書き込みについて言えば、半導体式のキャッシュメモリを搭載し、一度メモリで受けてからディスクに書き込むような仕組みを有することが一般的です。
半導体式では、SSDやUSBメモリメモリ、メモリカードがありますが、いずれもランダムアクセスに強いです。
一方で、光学式のCDやDVDなどは光を使ってディスク面を変性させ読み書きをおこなうため、磁気ディスク同様にランダムアクセスが苦手な傾向にあります。
HDD(Hard Disk Drive)

HDDは磁性体を塗布した金属またはガラスのディスクを磁化させることで情報を保持します。ディスクを回転させながら磁気ヘッド(読み書き素子)が搭載されたアームを動作させてデータにアクセスします。
ディスクの回転速度が早いほどデータアクセス・読み書きが速く行えます。
稼働する次回要素(ディスク回転・アーム旋回)を含むため衝撃耐性が低い傾向にあります。
データアクセス時の平均待ち時間は平均回転待ち時間+平均位置決め時間として計算されます。
SSD (Solid State Drive)

SSDは記憶素子にフラッシュメモリを用いた補助記憶装置です。システムのインターフェイスは前記事でものべたようにHDDと共通でS-ATAなどを用いることが一般的です。機械部分を持たないため衝撃耐性が高いです。ランダム呼び出しが早く、発熱量が小さいことから読み書き速度が重視されるシステムではHDDよりもSSDが採用されます。
一方で記憶素子の書き換え可能回数が少ないことから寿命を考慮したシステム設計が必要です。HDDに比べ高価で容量が小さい傾向があります。
まとめ
出力装置と補助記憶装置についてまとめてきました。
これで9記事を通したプロセッサからはじめメモリ、バス、入出力IF、入出力装置とコンピュータの構成要素について解説をお終えました。
すべてお読みいただいたあなたはかなりコンピュータに詳しい人と言えると思います。
次回からは組込みシステムの構成要素について解説をしていきます。システム設計や評価方法等より実践的な内容が含まれていくのでお楽しみに!